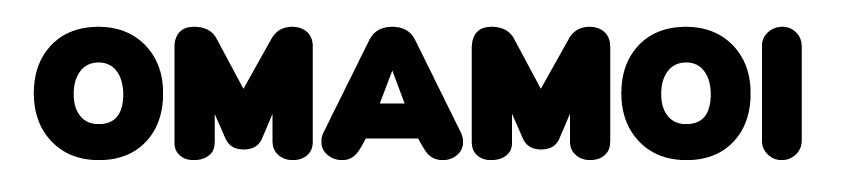目次
はじめに
お守りは持つ人を守ってくれる大切なものですが、役目を終えた後はどう処分すればいいのか迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、神社仏閣で一般的に推奨されている お守りの正しい処分方法とマナー を解説します。
お守りの処分はなぜ必要?
- お守りには「期間」があるとされ、基本的には 1年を目安に交換・返納 するのが習わしです。
- 長期間同じお守りを持つこと自体は問題ありませんが、汚れや傷みが出てきたら感謝を込めて処分するのが望ましいとされています。
お守りの処分方法
1. 神社・寺院に返納する
- 購入した神社や寺院に持参して「古札納所(こさつのうしょ)」に納める。
- 遠方で行けない場合でも、最寄りの神社・寺院に納めることが可能。
2. 焚き上げに出す
- 正月や節分の行事で行われる「どんど焼き」で、古いお守りを焚き上げてもらえる。
- 火により清められ、感謝とともに天へ返す意味がある。
3. 郵送で返納できる神社もある
- 近年は郵送で古いお守りを受け付ける神社もあり、遠方の人でも安心。
- 神社の公式サイトを確認し、指定の手順で送付する。
自宅で処分する場合のマナー
どうしても神社や寺院に持ち込めない場合は、以下の方法が一般的です。
- 半紙や白い紙に丁寧に包む
- 塩で清める(軽くひとふり)
- 可燃ごみとして処分
このとき「これまで守ってくれてありがとう」と感謝を伝えることが大切です。
お守りの処分タイミング
- 一般的には 1年ごとに新しいお守りに取り替える
- 合格祈願や安産祈願など、目的を達成した時点で返納
- 特別な記念品として取っておきたい場合は、清潔に保管するのも一つの選択肢
まとめ
お守りは、持つ人の無事を祈って授与された特別なもの。
役目を終えたら、神社・寺院に返納するのが基本ですが、どうしても難しい場合は感謝を込めて自宅で処分しても構いません。
👉 大切なのは「粗末に扱わないこと」と「感謝の気持ちを忘れないこと」。
正しい処分を心がけて、お守りのご利益に感謝を伝えましょう。